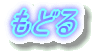※ 生活スキル獲得が進みにくく、将来自立生活に支障が出そうであれば、「生活に必要な知識学習」を行います。
※ 当所での支援は、「支援方法」 で述べていることがベースになっています。
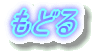
「こころ」は、こんなところです。
(対象となる方)
不登校、引きこもり、職場に適応しにくい、コミュニケーションや対人関係が取りにくい、感情のコントロールがつきにくいこと、物事の捉え方に偏りや歪、生活スキルの獲得が不十分など、適応的生活が進みにくい状態にある当事者やその家族の方 (対象年齢は問いません)
(適応的な生活が進みにくい主な原因)
多くは、判断力の偏りや歪です。程度によっては、これがストレスを高めて心的疲労や不安を強め、さらに不適応状態が増すサイクルに陥り、結果、生活上影響が大きくなることです。通常、多くの当事者方は、不適応の原因へ意識が向きにくく、またその自覚が持ちにくい状態にありまず。
(目標として)
問題の解決や軽減とおおよそ社会・生活適応に支障がない程度を目指します。
(主な支援内容)
ステップ1
判断力や行動が対人関係や生活(家庭、学校、職場など)に与えている負の影響を理解して受け止めます。
ステップ2
取り組むべき課題を自ら選定できるように協力します。
ステップ3
当事者の方が自ら方法を決めて取り組めるように協力します。
※ステップ1への導入には以下の条件を満たす必要があるので、その働きかけをします。
(信頼関係を築く、心をオープンにできること、自分に向き合える状態にあること)
※ステップ1〜3は、当事者自身が主体的に進められるように援助していきます。
※ 家族の方へは、当事者の状態の理解を深めていただき、家族としてできることの提案をします。
※ 当事者、家族の方から解決したいことや分からないことがあれば説明します。
※ 状態を把握するために必要あればその説明と同意あれば、「心理検査」を行います。
※ 生活スキル獲得が進みにくく、将来自立生活に支障が出そうであれば、「生活に必要な知識学習」を行います。
※ 当所での支援は、「支援方法」 で述べていることがベースになっています。