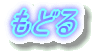そのときに大切なことがあります。
生きていく中での絶対条件を意識することです。
それは都合がいいこと悪いこと双方起こり、選択できないことなのです。自分にとってよいことは受け入れ、辛いことは受け入れ難いこと、辛いことを何とかしたいと思う反面、出来れば避けたい(考えたくない、気を紛らわしたい)と思うことす。
嫌なことから逃げる方へ舵を切れば、一時的には楽になりますが、今後も嫌なことを意識してそれを避けて生活をしていかないといけないし、再び嫌なことが起こらないように思い、不安を抱えながら生活することになります。
辛いことの内訳にはさまざまな要素がふくまれます。
気付きにくいのですが自分の心グセが招いたことも多くを占めているものです
しかし辛い現実の原因を環境因、運の良し悪し、他者に責を見出そうとしやすいものです。
そう判断すれば、自分の捉え方や判断に原因があると意識することは(事の起こりを正確に捉えていたかどうかを再意識すること)希薄になります。
それは、人間である以上、自己保存や自己都合を優先させる心理が働くためです。
さらに自分自身の判断力に偏りが強さに比例してより気付きにくい状態になり、原因の多くが外部にあると判断しやすく、ほとんどが「自分は悪くない」と結論を出してしまい事態に手をつけない状態にしてしまうのです。当事者がこのような認識をもっていると関わる方として、どうすべきか説明しても、なかなか聞き入れられない状態になっているので、辛い現実が続くことになります。これを避けるために繰り返し説明するのですが、当事者は自分より外部に責の多くあると捉えているので、理解は進みません。さらに繰り返し説明することで当事者、関わる方、双方に嫌悪感を強く抱くようにもなります。
ではどうすべきか?
それは関わる方が、当事者の現実を認めること、それは正しいとか正しくない、の意識で当事者と向き合わず、当事者の意識に添って事態を眺めることは極めて重要なことなのです。それは、判断したこと、取った言動に整合性を持ってみることで否定的な感情が薄まり、それが当事者に通じて肯定的に受け止められていると捉えられるとコミュニケーションがとりやすくなるものです。その訳は、相手にとって自分のことに興味をもたれていると感じてもらえるからです。さらに相手をより理解することは、相手を尊重することでもあるからです。この段階に至ったら当事者自身の意識と行動と結果に意識を向ける取り組みを行います。
相談場面で、「なぜいつもこうなるんだろう」「どうしてうまくいかないのか」のつぶやきを聞くことがあります。これは原因を捜し求めている証で、事態の変化や改善の入り口に立ったことを意味します。
その答えが、自分自身にあることを知ったとき、後悔とほぼ同時期に事態が好転、解決に向けて物事が動いていくのです。