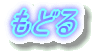
違いを受け入れること
人と自分は物事の捉え方、感じ方が違うことは当たり前なのですが、違いを確認すると違和感を感じたり、正しいと思う自分の基準と異なると、つい否定的に捉えてしまいやすいものです。
しかし違うことは事実なので、まずは受け止めること。
次に正しさにこだわらず、重要なのは、当事者の判断(言動含む)が生活適応においてどの程度の妨げになっているかを調べていくことです。
妨げが現在また未来において軽微であれば経過を見ますが、妨げが大きければ当事者に説明し理解して改善を促すわけです。
しかし、説明してもなかなか理解は進まないことが多いのです。
それは生活適応に支障が大きいほど、判断の歪みや偏りが強いため当事者は何が原因で不都合なことが起こっているかが分かりにくく、自分より、外に原因を求めるなど状況判断の誤認が多いためです。
不適切性の度合いと生活不適応性は比例しており、これに伴い心的苦痛、ストレスがさらなる判断力の歪みを助長することになって不適応性の持続と悪化を招くことになっていきます。
関わる方はこれらの現実を理解し、受け止める必要があるのです。
方法は、当事者の不適応の現実が主に自分の判断にあると認識に気づきにくいことにを強く意識して関わることです。すぐにとはいきませんが、当事者が受け入れられていると認識すれば徐々にコミュニケーションも取りやすくなり、そうなれば自己に向き合うよう促すことで自己の状態に徐々に気づいていくのです。